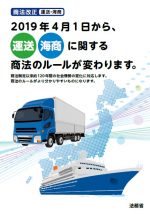令和元年10月1日から消費税率が8パーセントから10パーセントへ引き上げられることとなります。
これに伴い、貨物自動車運送事業者においても消費税の転嫁のための運賃及び料金の変更届出がなされることとなります。
消費税の適正かつ円滑な転嫁を図る観点から、消費税率の引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱について、各事業者においてご確認、ご対応いただきますようお願いいたします。
「運賃及び料金変更届出書」の提出について(解説)
(公社)全日本トラック協会作成 1.運賃及び料金の変更届出書を提出する必要がない場合 外税方式であり、届け出ている運賃・料金が「運賃・料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算する」等、具体的な現行の消費税率(8パーセント)を運賃料金適用方に記載していなければ、変更届出書を提出する必要はありません。 2.運賃及び料金の変更届出書の提出が必要な場合 総額表示(宅配、引越等)の場合は、届け出ている運賃・料金が消費税率引き上げにより上がることとなるので、変更届出書の提出が必要です。また、外税方式であっても、運賃料金適用方に「運賃・料金の総額に消費税(8パーセント)を乗じる」等、運賃料金適用方に具体的に「8パーセント」と記載している場合は変更届出書の提出が必要です。
なお、消費税率引上げのためのみの変更届出書は、主たる事務所を管轄する地方運輸局長等あてに(別紙2)の簡易な様式にて正本1通のみ(本来の提出部数は提出先+運賃・料金を適用する運輸局等の数)を提出することも可能とされています。 |
国土交通省、国税庁、農林水産省、経済産業省及び中小企業庁は、飲料配送の関係者や法律の専門家等を構成員とする「飲料配送研究会」を設置し、本年2月から飲料配送に係る貨物の毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について議論を重ね、このたび、「飲料配送研究会報告書」をとりまとめました。 あわせて、飲料配送中に貨物が毀損した場合の標準貨物自動車運送約款の適用細則を定めました。 |
飲料配送中の荷崩れ等により貨物に毀損が生じた場合、毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について、運送事業者と荷送人あるいは荷受人との間でのトラブルや、その処理や損害賠償等に関して一方の当事者の納得が十分得られない形で処理されるケースが発生しています。
国土交通省では、そうした場合において標準貨物自動車運送約款に従うとどのように処理すべきか、「飲料配送中に発生した貨物の毀損等に関する取扱いについて(貨物自動車運送事業法に基づく標準貨物自動車運送約款の適用細則)」を定めております。
飲料配送における貨物の毀損等に関する処理に関し、本適用細則を踏まえて、契約時に責任関係を明確化するとともに、貨物の毀損が発生した場合の処理についてご理解いただきますようお願い申し上げます。
本年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることとされており、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が制定・施行されているところです。
各事業者においては、あらためて下記リンク先をご参考に、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
望まない受動喫煙の防止を目的とした健康増進法の一部を改正する法律が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されているところです。
この改正法により、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられます。
今般、これらの施行を踏まえ、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、厚生労働省において「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されましたのでお知らせいたします。
各事業者においては新たなルールの適用について、ご対応いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
TEL 017-734-4113
参考
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。
改正の概要(荷主対策の深度化) (1)荷主の配慮義務の新設 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。 (2)荷主への勧告制度の拡充 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。 (3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置) ① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。
② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。
③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。
※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等 |
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室
TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575
 昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、これらについては本年夏頃から施行予定であることから、これをあらかじめ周知するため、国土交通省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省と連名のリーフレットを作成いたしましたのでお知らせいたします。
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、これらについては本年夏頃から施行予定であることから、これをあらかじめ周知するため、国土交通省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省と連名のリーフレットを作成いたしましたのでお知らせいたします。
なお、後日施行された際には、施行年月日を記載した同じ内容のリーフレットをあらためて掲載いたします。
 トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。
トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。
今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。
従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。
この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。
荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。
1.背景
トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。
2.乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業
[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し
[2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。
3.今後のスケジュール
施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)
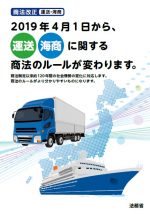 今般、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」(平成30年法律第29号)が公布され、平成31年4月1日から施行されました。
今般、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」(平成30年法律第29号)が公布され、平成31年4月1日から施行されました。
この法律は、商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、運送・海商関係の規律の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名口語体に改めることを主な内容としております。
法務省では、その趣旨をご理解いただくためにパンフレットを作成いたしました。下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の概要 ○ 今回の改正では、まず、陸上運送に関する改正前の商法第2編第8章の規定を海上運送・航空運送及び複合運送(陸・海・空を組み合わせた運送)にも妥当する総則的規律として位置付けることとし、これまで規定を欠いていた航空運送及び複合運送についても、商法の規律を及ぼすこととしています。 ○ また、今回の改正では、危険物の運送を委託する荷送人は、運送人に対し、その安全な運送に必要な情報を通知する義務を負うとの規定や、運送品の滅失等についての運送人の責任は、その引渡しの日から1年以内に裁判上の請求がされないときは消滅するとの規定を設けるなど、運送全般に関する規定の整備を行うこととしています。 ○ さらに、今回の改正では、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権のうち、財産権の侵害を理由とするものは、不法行為の時から2年間で時効により消滅するとの規定を設けるなど、海商全般に関する規定の整備を行うこととしています。 ○ このほか、改正前の商法のうち「第2編 商行為」の規定の一部(同編第5章から第9章まで)及び「第3編 海商」の規定については片仮名・文語体で表記されていたため、これらの規定を全て現代用語化することとしています。 |
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄績をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。
働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
働き方の多様化が進む一方で、長時聞労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状態です。
このため、今般、長時間労働の是正等、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。
今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、総合対策の見直しが行なわれましたので、各事業者において、「事業者が講ずべき措置」について取組んでいただきますようお願い致します。
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(項目) ■ 時間外・休日労働時間等の削減
■ 年次有給休暇の取得促進
■ 労働時間等の設定の改善
■ 労働者の健康管理に係る措置の徹底 |
上記措置に関する詳しい取り組み方法などは、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。