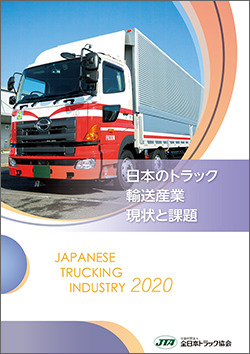平成29年に運輸安全マネジメントの基本的な方針及びガイドラインが改正され、運輸事業者が安全管理体制を構築・改善するにあたり、「自然災害への対応に関する社会的要請についても可能な限り取り入れていくこと」とされました。
今般、運輸安全マネジメントの一環として、運輸事業者の自然災害への対応力を向上させ、防災体制の構築及び実践に取り組むにあたってのガイダンスとなる「運輸防災マネジメント指針」が策定されましたのでお知らせいたします。
指針には、自然災害への対応として、安全管理体制の構築や事前の備え、関係者との連携や事前の教育や訓練の必要性などが示されており、国民生活・経済を支える重要インフラとして災害時にも事業継続が必要なトラック運送事業者による取組みが求められています。
なお、運輸防災マネジメントに関する今後のスケジュールは次の通りです。
○ 運輸事業者に対する説明会を地方運輸局ごとに開催します。参加しやすいよう、オンラインによる説明会も検討します。
○ 運輸事業者の取組に対する「防災マネジメント評価」を7月に開始します。
令和2年7月豪雨に係る特殊車両通行許可事務の最優先処理について、国土交通省道路局より通知がありましたのでお知らせいたします。
「令和2年7月豪雨」に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについては、当面の間、特殊車両の通行が、被災地域(※1)の早期復旧や物流確保等の観点から、令和2年7月豪雨による被災地域への又は被災地域からの貨物の運搬等である場合には、別添の様式(※2)を申請書に添付の上、申請先の事務所に電話等でご連絡頂いた申請について、最優先で処理を行うこととします。
なお、オンラインで申請される場合は、「申請書入力方法選択画面」で「災害時優先処理を希望する」ボタンをチェックのうえ申請書の作成をお願いします。
ただし、災害復旧対応等のため迅速な事務処理ができない可能性がありますので、ご理解をお願いします。
※1.被災地域(災害救助法適用地域)については下記リンク先をご確認ください。
※2.別添様式
全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2020」を令和2年7月7日に発行しました。
下記リンクより書籍(A4判・全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。
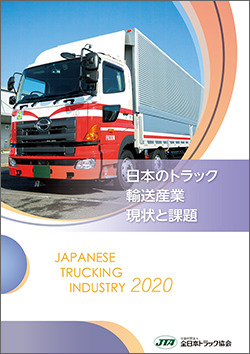
一般財団法人日本気象協会では、悪天候時の輸送安全を支援する物流向け新サービス「GoStop(ゴーストップ)マネジメントシステム」の提供を、2020年6月1日(月)から実施しておりますのでご案内いたします。
なお、本サービスは有料ですが、サービスのお試し期間も設けられております。
「GoStopマネジメントシステム」の3つの特徴
- 高速道路がどの場所でどのような気象現象によって輸送影響リスクが高いのか、ひと目で確認可能
- 走行する高速道路についてICごとに、72時間先まで1時間単位の輸送影響リスクを表示
- 台風が発生した際には、日本気象協会が保有する独自技術を使って示す詳細な台風進路予測や雨量、暴風予測などを、運行タイムラインに沿って台風上陸の最大7日前から提供
詳しい内容については下記リンク先をご覧ください。
お申込み、サービスに関するお問い合わせ(法人向け)
日本気象協会 防災ソリューション事業部 営業課
Tel:03-5958-8143
関連記事
青森河川国道事務所より、下北半島縦貫道路「野辺地~七戸間」の計画に関するアンケートへの協力依頼がございましたのでお知らせいたします。
下北半島縦貫道路は、下北地域の中心都市であるむつ市を起点とし、上北郡七戸町で東北縦貫自動車道八戸線と連絡する延長約60kmの地域高規格道路です。
現在、未事業区間である「野辺地~七戸」間の事業化に向け「概略ルート・構造の検討(計画段階評価を進めるための調査)」を推進しております。
本アンケートは道路計画検討を進めていく上で重要なものとなっておりますので、沿線にお住まいの方、事業者はもちろん、他地域の皆様にも広くご協力頂きます様、お願いいたします。
インターネットによる回答(6月8日~7月31日まで)
下記リンク先から、WEBアンケートにより回答をお願いいたします。
ハガキによる回答(7月1日~7月31日まで)
野辺地町、七戸町、東北町にお住いの方々には全世帯へ、青森市、八戸市、十和田市、むつ市、横浜町にお住まいの方々には無作為抽出した世帯にアンケート用はがきを配布いたします。
また、国道4号(野辺地町~七戸町間)を利用するトラック等の事業者にもはがきを配布いたします。
はがきは7月1日以降順次配布します。
回収ボックスによる回答(7月1日~7月31日まで)
河川国道事務所、県庁、各市役所・町役場・支所、道の駅などにアンケート調査票と回収ボックスを設置します。
アンケートに関するお問い合わせ先
青森河川国道事務所 調査第二課
電話 017-734-4570(平日9:00~17:00)

内閣府 中央防災会議より、これからの本格的な梅雨及び台風シーズンに向けた防災態勢の強化についての通達が発出されましたのでお知らせいたします。
例年、梅雨期及び台風期においては、各地で局地的大雨や集中豪雨が観測され、河川の急な増水・氾濫、がけ崩れ、土石流、地すべり、高潮、竜巻などにより、多数の人的被害及び住家被害が発生しています。
令和元年東日本台風では、特に静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方の多くの地点で記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、約100名の死者・行方不明者が発生する等、各地で甚大な被害が発生しました。
これから、梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、人命保護を第一に、災害発生の恐れのある箇所の確認、市町村が行う避難勧告への対応などについて遺漏の無いよう取り組んで頂きますようお願いいたします。
なお、現在新型コロナウイルスの感染拡大防止への対応が急務な状況にあるため、各取り組みの実施に当たっては、当面、各機関及び地域の実情に応じて可能な範囲・方法により実施していただきますよう、重ねてお願いいたします。
防災関連リンク
消防庁では、平成30年7月豪雨や台風21号等により、危険物施設においても多数の被害が発生したことを踏まえ、「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討会」を開催し、調査・検討を行いました。
この度、検討報告書(令和元年度)及び「危険物施設の風水害対策ガイドライン」がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
トラック事業者に関連性の高い項目としては、
・地下タンク貯蔵所における風水害対策上のポイント(12ページ目・別紙5)
・移動タンク貯蔵所における風水害対策上のポイント(16ページ目・別紙7)
等がございます。
上記ガイドラインをダウンロードし、ご確認ください。
今後、融雪出水期を迎えるにあたり、気温上昇に伴う 雪崩及び落雷の発生や、融雪に伴う出水による河川の氾濫及び 土砂災害や地すべりによって被害が発生するおそれがあること等 から、今般、中央防災会議会長(内閣総理大臣)より「融雪出水期 における防災態勢の強化について」(令和2年3月10日付け 中防災第8号)による通知がありましたのでお知らせいたします。
トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。
他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。
今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。
1.異常気象時における措置の目安 下記別表のとおり。
なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。 2.輸送を中止した場合の対応 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。 3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。 4.その他 (1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。 (2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。 (3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。 |
【別表】異常気象時における措置の目安
| 気象状況 | 雨の強さ等 | 気象庁が示す車両への影響 | 輸送の目安※ |
| 降雨時 | 20~30㎜/h | ワイパーを速くしても見づらい | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
| 30~50㎜/h | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | 輸送を中止することも検討するべき |
| 50㎜/h以上 | 車の運転は危険 | 輸送することは適切ではない |
| 暴風時 | 10~15m/s | 道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
| 15~20m/s | 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる |
| 20~30m/s | 通常の速度で運転するのが困難になる | 輸送を中止することも検討するべき |
| 30m/s以上 | 走行中のトラックが横転する | 輸送することは適切ではない |
| 降雪時 | 大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき |
| 視界不良(濃霧・風雪等)時 | 視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき |
| 警報発表時 | 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき |
※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。
この件に関するお問い合わせ
青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
(追記)3月11日を予定していた東日本大震災九周年追悼式につきましては、現下の状況を踏まえ、開催を取りやめることとなりました。
東日本大震災九周年追悼式が、令和2年3月11日(水)午後2時30分から国立劇場(東京都千代田区隼町4-1)にて行われます。
国民の皆様には、3月11日(水)午後2時46分に、それぞれの場所において黙とうをお願いいたします。