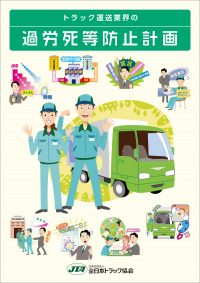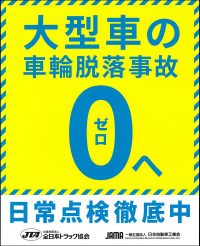全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和元年11月末現在の合計223件で、昨年同期と比較して1件増となりました。
<11月単月>
大 型:14件(昨年同月比 ±0)
中 型:7件(昨年同月比 -1)
準中型:4件(昨年同月比 +3)
普 通:1件(昨年同月比 ±1)
「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。 ・2020年までに死者数を200人以下 ・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標) |
これから本格的な降積雪期を迎える中、各事業者(所)においては、次の事項について留意し、輸送の安全確保等、事故の防止に努めるようお願いします。
気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。 - 積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンを装着するよう徹底を図ること。なお、スタッドレスタイヤへ交換する際は、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理を確実に行うこと。
- 点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。
- 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
- 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行計画の変更及び利用者への情報提供等の適切な措置を講ずること。
- 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。
|
関連記事
国土交通省及び警察庁において、昨年12月から「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部改正が施行されており、標識により規制された区間においては、異例な降雪時のタイヤチェーンを装着していない車両の通行が禁止されています。
関連記事
全日本トラック協会では、下記リンク先にて「雪道対策について」のコーナーを設け、雪道対策や道路情報のリンクを掲載しておりますので、これらの情報もご活用ください。
12月4日、バスが東京都新宿区の都道を走行中、ハイヤーに追突し、さらに中央分離帯を乗り越え、街路灯に衝突し止まり、ハイヤーの運転者が死亡する事故が発生しました。事故の原因については調査中ですが、当該バスの運転者が事故後に搬送された病院にて、インフルエンザに罹患していたことが判明しました。
一般的に、インフルエンザウィルスに感染してから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、発熱(通常38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然現われるとされております。(参考 国立感染症研究所HP)
自動車運送事業者におかれましては、乗務前点呼時において、体調が正常であった場合においても、運転者が運行中に体調が急変し運行に悪影響を及ぼす場合もあることから、事業用自動車の安全確保に万全を期すために、下記事項について改めて徹底をお願い致します。
自動車運送事業者は、以下のことを改めて徹底するとともに、安全に運行をすることができないおそれがある状況での運行を行わないこと。 - 運転者に対して運行中に体調の異変を感じた時に、無理に運行を続けると非常に危険であることを理解させ、運行中に体調の異常を少しでも感じた場合、速やかに営業所に連絡する等の指導を徹底すること。
- 運行中の運転者の体調変化等による運行中止等の判断・指示を適切に実施するための体制を整備すること。
- 運転者が体調異変等の報告をしやすいような職場環境を整備すること。
- 職場内におけるうがい、手洗い及び消毒用アルコールを使用した手指消毒の徹底すること。
|
自動車事故対策機構では令和元年度下期の運輸安全マネジメント認定セミナー(ガイドラインセミナー)を、下記のとおり開催することと相成りましたので、ご案内申し上げます。
セミナーの内容
ガイドラインセミナーは、国土交通省が定める「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」の14項目の要求事項について、具体的な事例を交えて解説する内容となっております。
そのため、「これから安全管理体制の構築を目指す事業者の方」や「新たに運輸安全マネジメントの担当になった方」向けの内容となっております。
セミナーの開催日程等
(1)開催日時 令和2年1月30日(木) 13:00~16:30(受付開始12:30~)
(2)開催場所 グランドサンピア八戸(青森県八戸市東白山台1-1-1)
受講することによる監査インセンティブ
受講された方には、「受講済証」を発行いたします。なお、経営管理部門の要員が認定セミナーを受講し、受講内容を活用して、安全管理体制の構築・強化に取り組んでいる場合は、監査インセンティブがあります。
※ 一般貸切旅客自動車運送事業者様につきましては、監査方針の改正により、上記インセンティブが発生しませんので、受講の際はあらかじめご注意下さい。
個人情報の取り扱いについて
国土交通省の通達により、セミナー実施者(当機構)は国土交通省に対し「事業者名、受講者の氏名、受講した認定セミナー」を通知することが定められております。特に不合がない場合は申込書にて同意をお願いいたします。
定員・受講料等
(1)定員20名
※ 定員になり次第締切りとなります。また、参加者僅少の場合開催中止となることがあります。あらかじめご了承ください。
(2)受講料 5,200円(税込。テキスト代含む)
申込方法
下記リンク先より「ガイドラインセミナー申込書 兼 受講票」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、(独)自動車事故対策機構 青森支所あてファックスにてお申し込みください。
お問合せ先
(独)自動車事故対策機構 青森支所
〒030-0843青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3F
TEL 017-739-0551
東京2020大会競技会場等の周辺の交通混雑を緩和するため、会場周辺の交通対策として、東京圏の各会場ごとに、進入禁止エリア、通行禁止エリア、迂回エリア、専用レーン・優先レーンの素案を掲載していますので、下記リンク先サイトをご覧下さい。
関連記事
本年12月2日付で、青森県警察本部交通部長より、交通事故抑止に向けた取組について(依頼)の通達が、青森県トラック協会長あてに発出されました。
(公社)青森県トラック協会 会長 木村英敬 殿 青森県警察本部 交通部長 吹越一人 交通事故抑止に向けた取組について(依頼)
謹啓 師走の候、貴台におかれましては、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
平素から交通安全活動をはじめ、警察業務各般にわたり、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 さて、本年の交通事故死者数を見ますと、11月末現在では34人と前年同期比で6人の減少となっており、第10次青森県交通安全計画で掲げる交通事故死者数38人以下という目標達成が実現可能なところまできております。 しかしながら、11月中の死者数は5人と前年よりも増加し、更には、例年12月は交通死亡事故が多発する傾向にあることから、決して油断できる状況ではありません。 特に、年末は多忙に伴う業務・職業運転中や飲酒が絡む重大事故の発生が懸念されるところであります。 県警察といたしましては、このような情勢を踏まえ、年末に向けて交通指導取締りと、これと連動した広報啓発活動に取り組んでまいります。 貴台におかれましても、昼夜を問わず車両運転に従事しておられます貴協会傘下の事業所に対しまして、深夜・早朝の交通閑散に気を許した運転をしないことや、目的地に急ぐあまり他者への注意が散漫にならないようにすることなど、交通安全意識の高揚を図っていただければ幸いです。 また、12月1日に改正道路交通法が施行され、運転中の携帯電話使用等に対する罰則が強化されました。重ねて周知していただくようお願い申し上げます。 時節柄、何かと御多忙のところと存じますが、県内から悲惨な交通事故を発生させないためにも、何卒御高配を賜りますようお願い申し上げます。 敬具 |
会員各事業所においては、引き続き交通事故の抑止や安全・安心な輸送の確保につきまして、あらためて徹底したいただきますようお願いいたします。
国土交通省では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の交通混雑緩和に向け、発側及び着側の荷主企業と物流事業者が連携し、サプライチェーン全体での物流効率化に向けた取組を実施していただくよう、東京都、大会組織委員会、関係省庁と共にお願いを発出しましたので、お知らせいたします。
大会期間中は選手や大会関係者等の道路利用により、首都高速道路では1日あたり約7万台の交通量が増加し、何も対策を施さなければ、首都高速道路における渋滞の悪化や、都心に向かう一般道における渋滞の発生が見込まれております。
そのため、東京都、大会組織委員会、国においては、「2020TDM推進プロジェクト」として、大会開催時の交通量の抑制や分散、平準化を行う「交通需要マネジメント(TDM)」を推進し、円滑な大会輸送の実現と経済活動の維持との両立を目指すこととしております。
このたび、発側及び着側の荷主企業と物流事業者が連携し、サプライチェーン全体での物流効率化に向けた取組を実施していただくよう、東京都、大会組織委員会、関係省庁と共にお願いを発出しましたので、お知らせいたします。
国土交通省としましては、今後とも、物流事業者・荷主企業への働きかけや一般消費者への呼びかけ等、TDMの一層の効果発揮に向けた取組を進めて参ります。
睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、平成30年6月1日より睡眠不足のドライバーを乗務させてはならず、点呼時にドライバーに対して睡眠の状況を確認することが義務付けられました。
また、全日本トラック協会では、過労死の根絶を図るために策定した『過労死等防止計画』の対策3に「睡眠時間の確保と規則的な運行」を掲げ、ドライバーに良質な睡眠の確保が、安全と健康の基盤であるということを教育する、睡眠の重要性をドライバーに認識させることを訴えております。
そこで、今般、全日本トラック協会では「トラックドライバー睡眠マニュアル」を作成しました。
本マニュアルでは、トラックドライバーに知ってもらいたい睡眠の情報を、実践編と知識編に分けて記し、また、運行管理者が点呼の睡眠チェック時にどのような点に着目したらよいのかについても記載しました。
ドライバーは良い睡眠を取る、運行管理者は良い睡眠を取らせることができるよう、本マニュアルをぜひご活用ください。
【参考資料】
青森県では、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし、「令和元年 冬の交通安全県民運動」を実施します。
期間
令和元年12月11日(水)~12月20日(金)の10日間
運動重点
1.子供と高齢者の安全な通行の確保
2.高齢運転者の交通事故防止
3.飲酒運転の根絶
4.冬道の安全運転の推進
5.踏切事故の防止
冬は積雪などにより路面状況が悪く、また、日没も16時台となり、運転には特に注意が必要です。
歩行者は、明るい色の服装や反射材を着用しましょう。
また、年末年始は飲酒の機会も増えます。飲酒運転は絶対にやめましょう。
近年、大型トラック(車両総重量8トン以上)のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故が急増していることを受け、今般、国土交通省より事故の発生状況及び車輪脱落事故防止に係る取り組みについて報道発表がありました。
【関連記事】
全ト協では、車輪脱落事故の発生状況等のデータとともに、車輪脱落を防ぐための具体的な対策を記したリーフレットを作成いたしましたので、日常点検及び定期点検の確実な実施に努めるとともに車輪脱落事故防止の徹底をお願いいたします。
また、(一社)日本自動車工業会(自工会)においても、タイヤ交換作業時の注意点や交換後の増し締めや日常点検などの重要性を注意喚起しています。