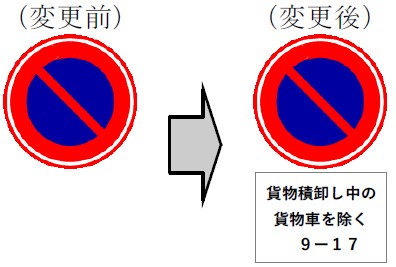衝突被害軽減ブレーキ、 ドライブレコーダー、IT点呼機器などの安全支援機器導入 及び、社内教育の充実に関する補助事業として、「令和3年度 事故防止対策支援推進事業」が国土交通省により実施されますのでお知らせいたします。
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付を開始いたします。
実施される補助事業は次の4種類で、いずれも 中小企業者(※1)であり、過去3年間に行政処分(※2)を受けていない事業者が対象です。
なお、車両の保有台数が5両未満の営業所は補助対象外となります。
※1 中小企業者とは、資本金3億円以下又は従業員300人以下であること。
※2 警告・勧告は含みません。
1.先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
(1)受付期間
令和3年8月2日~令和3年11月30日
(2)対象機器・装置
※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象
① 衝突被害軽減ブレーキ
※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの
② ふらつき注意喚起装置・車線逸脱警報装置・車線維持支援制御装置
※ 車両総重量3.5t超22t以下のトラックへ(13t超トラクタ含む)装着されるもの
③ 車両安定性制御装置
※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの
④ ドライバー異常時対応システム
⑤ 先進ライト
※ 車両総重量3.5t超のトラック(13t超トラクタ含む)へ装着されるもの
⑥ 側方衝突警報装置
※ 車両総重量3.5t超のトラック
(3)補助額
取得費用の2分の1(1車両当たり上限:①③④⑤10万円、②⑥5万円、①~⑥合わせて15万円)
2.運行管理の高度化に対する支援
(1)受付期間
1次募集 令和3年8月16日~令和3年9月17日
2次募集 令和3年10月4日~令和3年11月30日
(2)対象機器・装置
※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象
① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計
② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター
(3)補助額
① デシタル式運行記録計
車載器本体 3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)
② ドライブレコーダー
車載器本体 3分の1(1台あたり上限2万円)
カメラ 3分の1(1台あたり上限0.5万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)
1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円
3.過労運転防止のための先進的な取組に対する支援
(1)受付期間
令和3年8月16日~令和3年11月30日
(2)対象機器・装置
※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象
国土交通大臣が認定した次の機器
① ITを活用した遠隔地における点呼機器
② 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
③ 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
④ 運行中の運行管理機器
(3)補助額
取得費用の2分の1(1事業者あたり上限:80万円)※一部の機器に1台あたりの上限あり
4.社内安全教育の実施に対する支援
(1)受付期間
令和3年8月16日~令和3年9月17日
(2)対象
国土交通大臣の認定を受けている事故防止コンサルティングメニュー
(3)補助額
費用の3分の1(1事業者あたり上限100万円)
交付要綱・様式などは下記リンク先をご覧ください。