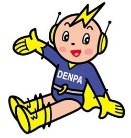建設業や製造業等をはじめ、様々な事業活動に伴って排出された産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理する必要がありますが、いまだ法律の趣旨や内容等が十分に理解されず、不適正な処理や不法投棄等が絶えない状況にあります。
また、本県は全国的にごみの排出量が多く、平成28年度の県民1人1日当たりのごみ排出量を見ると、事業所から排出される事業系ごみが全国平均を大きく上回っており、事業系ごみの減量化が課題になっているほか、リサイクル率についても全国平均と大きな開きがあります。
これらのことから、廃棄物処理制度への理解を一層深めていただくとともに、事業所から排出されるごみの減量・リサイクル推進を図るため、青森県主催の講習会が6月15日から29日の間、県内各地にて開催されることとなりましたので、この機会に受講いただきますようご案内申し上げます。
お問い合わせ先
【廃棄物処理法説明会に関すること】
青森県環境生活部 環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248
【ごみ減量・リサイクル推進講習会に関すること】
青森県環境生活部 環境政策課 循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249
無線局を利用するためには、原則として免許を受ける必要がありますが、免許を受けなければならないことを知らないで、無線局を開局するケースが後を立ちません。
そのため、総務省では、不法無線局の未然防止を図り、電波利用環境の保護を図ることを目的として、「電波利用環境保護周知啓発強化期間」(毎年6月1日から10日まで)を設け、電波の利用に対する正しい知識等の周知・啓発活動を実施しています。
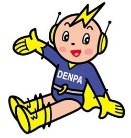
不法電波退治イメージキャラクター 「デンパ君」
電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電波は、こんな大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。
電波の混信・妨害についてのお問い合わせは 総務省 東北総合通信局 相談窓口 022-221-0641までお願いいたします。
八戸市環境保全課から「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について」の周知依頼がありました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)に報告書を提出することが義務付けられています。
- 八戸市に報告が必要な方
八戸市内の事業場又は工事現場から産業廃棄物を排出した事業者の方
- 報告内容
八戸市内で排出した産業廃棄物を処理するため、平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月30日)に交付したマニフェストの交付状況(※ 電子マニフェストを使用した場合、報告は不要です。)
- 報告期限
平成30年6月30日(土)
- 報告先
八戸市環境保全課(八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階)
- 報告方法
窓口への持参(月~金8:15~17:00)、郵送又はFAX
なお、法改正により、平成30年度から様式の一部が変更となっておりますので、市のホームページ(下記)から最新の様式をダウンロードして報告するようお願いいたします。
青森県では、県内で発生する食品ロス削減を目指し、食品ロス削減に配慮した取組を行う事業者を「あおもり食べきり推進オフィス・ショップ」として認定することといたしました。
各事業所においては、制度をご理解いただくとともに「あおもり食べきり推進オフィス・ショップへの認定申請」につきましてご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 認定要件
青森県内に所在し、事業活動を行っている事業所であって、もったいない・あおもり県民運動の趣旨に賛同し、別添の実施要綱別表2に掲げる「食品ロス削減に配慮した取組項目」のうち1以上の項目に取り組んでいること。
- 認定を受けた場合
県から認定証及び認定ステッカー(ショップのみ)を交付します。また、県が作成する普及啓発グッズ等を定期的に配付します。県のホームページ等を通じて、県民に事業者の取組をPRするほか、優れた取組を行う事業者を「もったいない・あおもり賞」として表彰します。
- その他
認定を希望する場合には、青森県環境生活部環境政策課までFAX等で申請書を送付してください。その他、あおもり食べきり推進オフィス・ショップ認定制度に係る詳細は、県ホームページを御覧下さい。
国土交通省では、地域交通のグリーン化に向けた次世代環境対応車普及促進事業として、ハイブリッドバス・トラック、CNGバス・トラックの導入支援を実施いたします。
運送事業者等を補助対象者とし、通常車両価格との差額の1/3を補助する制度です。
なお、交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要となります。
※ 交付予定枠の申請期間・・・平成30年9月3日(月)~9月28日(金)
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
環境省では、2003年より国民の皆様に日常生活の中で地球温暖化対策を実施する契機としていただくことを目的として、ライトアップ施設や家庭の照明を消していただくよう呼び掛ける「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」を実施しております。
今年度も6月21日(木)から7月7日(土)までを啓発期間としてキャンペーンを推進いたします。
また、6月21日(木)〔夏至〕と7月7日(土)〔クールアース・デー〕の20時から22時までの2時間を特別実施日として設定し、全国のライトアップ施設や各家庭の照明の一斉消灯を呼び掛け、参加施設数と削減消費電力量を集計いたします。
当該趣旨にご理解をいただき、キャンペーンにご協力いただきますようお願いいたします。
■6月21日(木)~7月7日(土)のキャンペーン期間中は可能な範囲で消灯を行いましょう。
■6月21日(木)と7月7日(土)の両日は、ライトアップ施設や家庭照明を20時~22時まで一斉消灯を行いましょう。
5月中旬より下記ホームページにてキャンペーン参加登録を行います。
一般財団法人 環境優良車普及機構では、環境省補助金を活用し、中小トラック運送事業者に対して燃費性能の高い低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援し低炭素社会を創出する事業を実施することとなりましたのでお知らせいたします。
【補助事業の概要】
本事業は、中小トラック運送事業者が低炭素型ディーゼルトラックの導入に要する経費に対して、当該経費の一部を補助する事業です。
<申請受付期間>平成30年6月11日(月)~平成31年1月31日(木)まで
【公募説明会】
5月18日から、全国各地にて公募説明会が開催されます。
東北地方では、5月24日に福島県郡山市にて、5月25日には仙台市にての開催となります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
暴走行為、過積載などを目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、大気汚染、騒音などの環境悪化の要因となっており、社会的にもその排除が強く求められています。
また、違法であるとの認識が無いまま改造を行っている自動車使用者や、車検後に部品の取り外しや取り付けを行って不正改造を行ったり、検査の合格を強要する悪質なケースもあります。
さらに、速度抑制装置の不正改造をほう助したとして、改変を行う部品を販売した者や、シートベルト警報装置を解除する用品を販売した者が逮捕されるなどの事案も発生しております。
国土交通省では不正改造についての認知度を高め、車両の安全確保、環境保全を図るため「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開しますので、各事業者においても下記実施要領に基づき、本運動への取り組みを行っていただきますようご理解ご協力をお願い申し上げます。
また、「不正改造防止自主点検票」を活用し、所有車両等について定期的な自主点検の実施に努めるよう、重ねてお願いいたします。

チラシ「不正改造車排除」強化月間
全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年4月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。
「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。
公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団では、優れたエコドライブ活動を実践している事業者を表彰する「平成30年度エコドライブ活動コンクール」を開催することと致しました。
今年度も、事業部門(緑ナンバー)、一般部門(白ナンバー)、ユニーク部門に分けて審査が実施され、最も優れた事業者には、事業部門では国土交通大臣賞、一般部門では環境大臣賞が授与される予定です。
参加費用は無料ですので、大臣賞を目指して、ぜひ当コンクールへの参加をご検討ください。