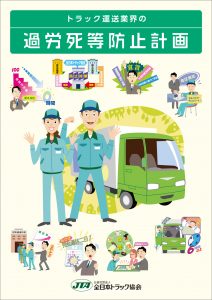10月28日、神奈川県横浜市の国道を走行中のバスの運転者が意識を失ったことにより高架橋の立柱及び乗用車に衝突し、乗客が死傷する事故が発生しました。
また、11月1日にも、千葉県成田市の県道を走行中のバスの運転者が心筋梗塞のため意識を失ったことにより信号機などに衝突する事故が発生し、運転者が死亡しました。
これらの事故の原因については調査中ですが、事業用自動車の運転者の意識消失による事故については、本年6月にも同種の事故が発生したことを踏まえ、「健康起因事故の防止に向けた健康管理の実施について」(平成30年6月8日付、国自安第35号)により、健康起因事故防止のための取組を徹底するようお願いしたところです。
今般、このような事故により乗客及び運転者が死傷するという事態が生じたことを踏まえ、各事業者においては「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成22年策定、平成26年改訂)等による運転者に対する健康管理を、運転者毎の状況に応じて適切に行っていただきますようお願いします。
※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
厚生労働省では、10月1日(月)から7日(日)まで、平成30年度「全国労働衛生週間」を実施します。
今年のスローガンは、「こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革」です。このスローガンは、こころとからだ両方の健康づくりを進め、職場で一丸となって働き方改革を進めることで、誰もが安心して健康に働ける職場を目指すことを表しています。
今年で69回目となる全国労働衛生週間は、昭和25年から毎年実施しており、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的としています。
毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場において、職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組を実施して頂きますようお願いいたします。
厚生労働省では、平成30年6月1日に睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正施行されたことを踏まえ、「交通労働災害防止のためのガイドライン」を改正しました。
本ガイドラインに基づき、次の各項目を重点的に、安全管理体制の確立、適正な労働時間等の管理や走行管理、安全衛生教育の実施、意識の高揚、荷主・元請け事業者による配慮、自動車運転者の健康管理の実施等について取り組みましょう。
- 睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理
- 乗務開始前の点呼等の実施
- 早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成
改正されたガイドライン等は下記リンクからダウンロードできます。
6月3日、富山県の東海北陸道を走行中のバスの運転者が意識を失ったことにより、当該バスがセンターポールを倒して対向車線の側壁に接触し、異変に気づいた乗客数名がハンドルとブレーキを操作することによりバスを停車させた事故が発生しました。
また、6月1日にも、東京都の上野公園横の道路を走行中のバスの運転者が意識を失ったことにより当該バスが側壁に衝突する事故が発生しました。
これらの事故の原因については調査中ですが、事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事故については、毎年多く発生しており、国土交通省としては、自動車運送事業者に対して、法令に基づく運転者の健康診断の実施を始めとした運転者に対する健康管理を適切に行っていただくため、次の手引き書を策定し、運転者の健康起因事故防止のための取組を行っていただくことを推奨しています。
各事業者におかれましては、この機会に改めて下記マニュアル等による運転者の健康管理を適切に実施いただくようお願いします。
※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
全日本トラック協会の「労働安全・衛生委員会」では、過労死等の根絶を図るため、2017年4月、関係行政機関の協力のもと、各界の有識者等で構成する「過労死等防止計画策定ワーキンググループ」を設置し、トラックドライバー等の過労死問題の究明に着手し、実効性のある過労死防止対策を計画的かつ着実に行う方策等について検討し、脳・心臓疾患による過労死等の発症を5年後までに20%削減すること等を目標に掲げた「過労死等防止計画」(2022年までの5カ年計画)を2018年3月に策定いたしました。
この度、この「過労死等防止計画」を分かりやすくまとめた「トラック運送業界の過労死等防止計画」パンフレットを作成いたしましたので、トラック運送事業者等関係者一丸となって本過労死等防止計画に掲げられた項目の着実な実行に向けて取り組んで下さいますようお願い申し上げます。
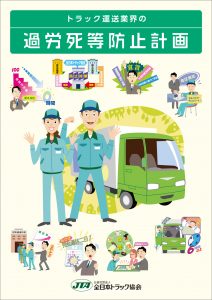
このパンフレットは全ト協機関紙「広報とらっく7月1日号」に同封されます。
全日本トラック協会では、過労死や健康起因事故につながる、脳・心臓疾患発症の要因となる高血圧の予防には血圧測定が重要であることから、乗務前点呼時の血圧測定を推進しております。
今般、運行管理者が点呼時に運転者の血圧値を正しく測る方法や測定された血圧値の評価法について解説したパンフレットを作成しましたので、ご活用下さい。
事業用トラックによる交通事故が全体に減少傾向にあるのに対し、脳・心臓疾患や体調不良など、ドライバーの健康に起因する事故は、むしろ増加する傾向にあります。
このような状況を踏まえ、全日本トラック協会ではトラック運送事業者や運行管理者等が、トラックドライバーをはじめとする従業者に対して、より適切な健康管理指導が実施できるよう、トラック運送事業に特化した健康管理マニュアルを作成しましたのでご活用ください。 (平成30年4月改訂)
※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案が毎年増加しており、過去5年間でみても、その中で脳血管疾患が最も多くを占めることから、更なる脳血管疾患対策が求められるところです。
そうした中で、平成28年12月に道路運送法及び貨物自動車運送事業法が改正され、自動車運送事業者は運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない旨が、法律上明記されたところです。
今般、これらの状況を受け、産官学の幅広い関係者から成る「健康起因事故対策協議会」を開催し、自動車運送事業者が、運転者の脳健診の受診等、脳血管疾患対策を進めていくために知っておくべき内容を取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」が国土交通省において策定されました。
各事業者においては、運転者の脳血管疾患による事故の防止を図るため、本ガイドライン及び概要版を活用し、自動車運送事業者における脳健診の受診や治療の必要性についての理解の浸透及び自主的なスクリーニング検査の導入について推進して頂きますようお願いいたします。
特定健診とは
日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診を行います。
特定保健指導とは
特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。
生活習慣病は、一人一人が、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けることにより予防可能です。
ご自身の健康状態を毎年確認し、健康づくりにつなげていくことが重要です。1年に一度、特定健診を受診し、生活習慣の改善が必要な方は、特定保健指導を受けましょう。
まだ受診されていない方はご自身が加入している医療保険者(自営業の方は市区町村へ、会社等へお勤めの方(被扶養者を含む)は、お勤め先)までお問い合わせ下さい。
※お勤めの方で、事業者健診(お勤め先で実施する健診)を受診された方又は受診予定の方は、新たに特定健診を受診する必要はありません。